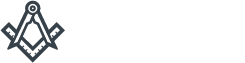公式ブログblog
2025/09/06 ChatGPT等のAIで論文作成はNG!?
【卒論×AIの“本当のリスク”まとめ|使う前に必読】

――「説明責任」を示せない卒論は、評価の土俵に乗らない。
1|制度面:卒論は“最終責任の可視化”が要件である
AIは著者になれない、最終責任は人間――これは国際的合意である(COPEの立場表明)。主要出版社(Elsevier/Springer Nature)も、AI使用は開示必須、本文・解釈・結論への説明責任は人間に帰属する方針である。卒論は「説明責任の訓練と証明」の到達点であり、AI依存で核心(問いの立て方、先行研究の読み込み、方法の妥当化、限界の自覚)を代替すれば、評価対象そのものを毀損する。各大学も、学位に直結する成果物は学生独自の成果であることを厳格に求めている(例:日本大学は「生成AIのみで作成は独自の成果物とみなさない」と明示)。この流れは文部科学省の留意点とも整合的で、機関ごとの方針に従う義務がある。
出典例:publicationethics.org/www.elsevier.com/springer.com/日本大学「自主創造」/文部科学省
2|評価面:検出ツールは“万能ではない”からこそ危険である
生成AI検出は偽陽性・偽陰性の問題が残る。Turnitin自身も限界を公表し、大学側も「検出=有罪」「非検出=無罪」とは扱えないと注意喚起している。卒論は“一点もの”評価で、疑義が生じた瞬間に、研究ノート・原データ・解析ログ・ドラフト履歴などで反証できなければ不利益は極めて大きい。すなわち「安易に使うほど疑われやすく、かつ無実の立証が難しい」という非対称リスクが働く。
出典例:turnitin.com/Vanderbilt University/lawlibguides.sandiego.edu/The Times
3|実務面:卒論は“プロセス評価”なのでAIと最も相性が悪い
テーマ設定→先行研究レビュー→方法設計→データ収集・解析→考察というプロセス自体が学習の中心である。要約・整文を超えたAI利用は、①誤要約・架空引用(幻覚)、②研究設計の自力検証の欠落、③図表・画像生成や改変に伴う権利・倫理問題、④翻訳・パラフレーズ時の出典不記載=剽窃評価の危険、を一気に高める。学部段階では原典精読や“自分の言葉での再構成”が評価の核心であり、「もっともらしいAI出力」は真価を曇らせる。出版社・学会もAI利用の透明性を強く求め、画像生成や査読へのAI投入を禁じる規定が拡大中である。
出典例:vascular.org/springer.com/Springer Nature
4|“どうしても使う”場合の最低ライン(それでも非推奨)
用途は言い換え・文法整形・目次案など“表現補助”に限定し、内容生成や先行研究レビューの代替はしない。AI利用は学内ポリシーどおり開示(ツール・版・用途・人手検証範囲)し、研究ノートにプロンプト概要・差分・採否理由を保存。引用・データ・図表は原典を人間が照合。指導教員の事前許可を得て運用設計を共有――これらを徹底すべきである。それでも最善は「不使用」である。
出典例:www.elsevier.com
5|アイブックス学術代行の役割(リスクの“見える化”和らげ)
安易なAI依存を止めることが第一である。同時に、疑義に耐える「説明可能性(Explainability)」を整えることが重要である。アイブックス学術代行は、
(a)学内規程×出版社基準の突合(MEXT方針・大学規程・COPE/Elsevier/Springerの要件整備)、
(b)原典照合・出典監査(DOI・版指定での照合、架空引用排除)、
(c)プロセス証跡パッケージ(ドラフト履歴・解析ログ・研究ノートの体裁化)、
(d)開示文テンプレート(投稿規程・学内様式準拠)
を提供し、“疑われにくく、説明できる”卒論作成を支援する。**方針は一貫して「内容生成への依存は避ける」**であり、学生本人のリーディングとロジック形成を最優先して伴走する。
出典例:文部科学省/publicationethics.org/www.elsevier.com/springer.com
※当サービスは“代筆”ではなく、倫理・コンプライアンスに沿った研究プロセス支援・編集支援・リテラシー向上のためのコーチングである。
— 結語 —
生成AIの安易な利用は、卒論の本質(独自の理解と説明責任)を侵し、検出の不完全さが“無実/有罪”双方の地雷を増やすため特に危険である。最善は不使用。やむを得ず最小限使う場合も、厳密な開示・原典照合・証跡保存と、指導教員の事前許可を前提にすべきである。アイブックス学術代行は“安全域の設計と監査”を提供し、学位審査に耐える透明性の確保を支援する。
#卒論 #生成AI #研究倫理 #アカデミックライティング #COPE #Elsevier #SpringerNature #文部科学省 #研究不正防止 #リサーチリテラシー #Turnitin
(参考ドメイン例:publicationethics.org/elsevier.com/springer.com/turnitin.com/mext.go.jp/日本大学「自主創造」サイト)
お問い合わせ
これまで日本全国・海外を含め10,000件以上のご依頼をサポートしてきました。経験豊富な相談員があなたのご要望にお応えする為、親身になって作成しております。負担の軽い納得料金で、迅速・的確な製作を行い、成果は確実にお約束いたします。
全国にいるアイブックスメンバーが責任を持ってお客様をサポート致します!
※お申込み時に担当責任者の経歴を送付しております!!